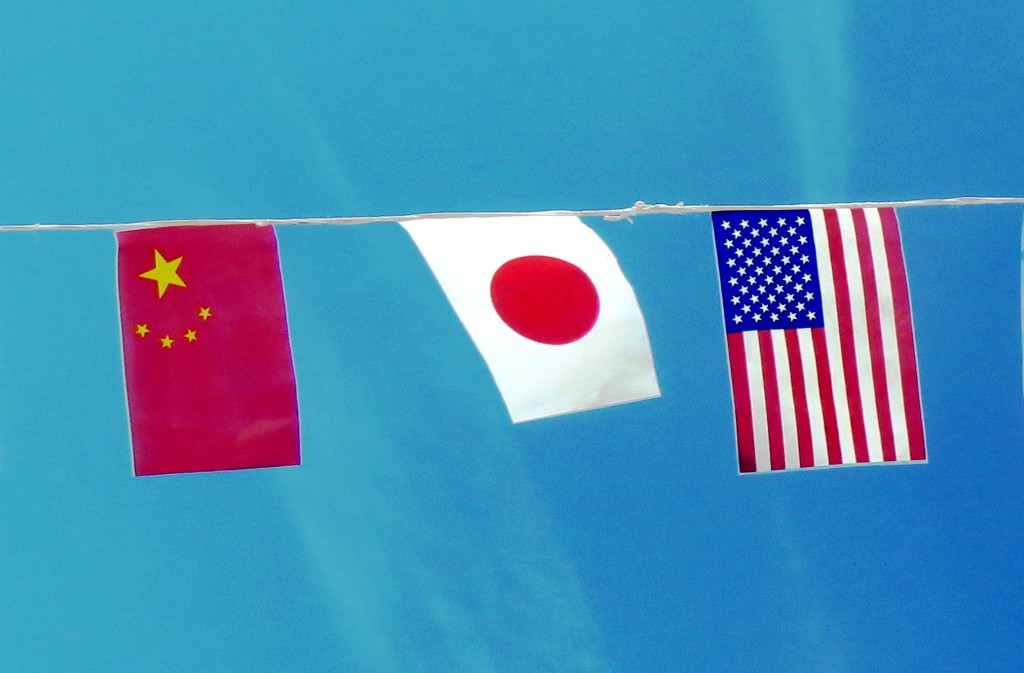日米同盟と、アジアの中での日本のあり方 / ドイツから見た日本の歴史問題
<今月取り上げた月刊誌>
『外交』(Vol.31)
『正論』『中央公論』『文藝春秋』(いずれも7月号)
◆ 2015年7月 ◆
1. 日米同盟と、アジアの中での日本のあり方/2. ドイツから見た日本の歴史問題
1. 日米同盟と、アジアの中での日本のあり方
◆「和解と誇りと希望と新時代の日米同盟へ」 安倍晋三首相インタビュー [正論]
◆「新世界地政学」 船橋洋一氏 [文藝春秋]
◆「和解と成長のアジアへ」 宮城大蔵氏 [外交]
◆「『共創』と『競争』の時代への新戦略」 大野泉氏 [外交]
各月刊誌とも、引き続き安倍外交が誌面を賑わせている。4月の一連の外遊を終えた安倍晋三首相は、『正論』7月号で「和解と誇りと希望と新時代の日米同盟へ」をテーマにインタビューに応じ、今回の訪米で感じた空気を伝えている。
この中で安倍首相は、2013年の首相就任直後の訪米とは打って変わり歓待を受けたエピソードを紹介している。「オバマ大統領には、たいへんなお気遣いをいただきました。訪米前、ケネディ駐日大使から『最近ご覧になった映画で、お気に召されたものはありますか』と尋ねられ、クリント・イーストウッド監督が伝説のバンド、フォー・シーズンズを描いた『ジャージー・ボーイズ』という映画に感銘を受けたという話をしていたのです。すると訪米中、なんと映画に出てきた『フォー・シーズンズ』の生演奏を聴くことが出来ました。ホワイトハウスでの公式晩餐会後のミニコンサートです」。安倍首相は、翌日のアメリカ連邦議会での演説のキーワードに「和解」を挙げたが、安倍首相の訪米を期に未来の協力関係構築を一気に進めたいという思いがアメリカ側にも強くあったことがうかがえる。
アジア太平洋地域における新しい国際秩序の枠組みとなるTPPやAIIBの進捗については、以下のように語っている。「TPPについては、私の訪米前に甘利明大臣(TPP担当相)とフロマン米通商代表部(USTR)代表が会談を行い、交渉をし、基本的には出口は近いという状況になっていると思います。大統領と私の会談でも早期の交渉妥結に向けて努力をしていくことで一致しました」「AIIBについては、アジアに膨大なインフラ需要があって、それに応えることのできる金融システムが重要だという認識では、日本と中国は一致しています。米国もその点は理解しているだろうと思います」。これを聞くかぎり、日本のメディアで報じられる主要国の不協和音をよそに、政策責任者同士の認識はむしろ共有されており、各国が国内世論などを踏まえた最適解を探っているように思えてならない。
アジアにおける日本の将来の立ち位置については、どのように考えているのだろうか。安倍首相は、AIIBへの加盟はまだ決定していないと前置きしたうえで、「いずれにせよ日本は、アジアの国々――AIIBでは域内国という言い方をしていますが――の発展に、責任ある立場として対応していかねばなりません。」と述べている。今後、アジア地域のインフラ需要に応えるため、独立行政法人国際協力機構(JICA)やアジア開発銀行(ADB)、国際協力銀行(JBIC)などによる施策を進め、「……民間資金も導入しながら質・量ともに十分なインフラ投資を、アジア地域で展開していく考え」だという。
■ 「米国のパワー低下」にどう対応するか
アジアにおける今後の日本の在り方を考える一つのカギであるAIIBへの加盟問題は、根強く月刊誌で議論され続けている。論点は参加・不参加それぞれのメリット・デメリットであり、台頭する中国の世界戦略に乗るか否かだ。ジャーナリストの船橋洋一氏は『文藝春秋』誌の連載「新世界地政学」で、AIIB問題の背景には、「米国のパワー低下」があると指摘している。
船橋氏は、「米国は、英国のAIIB加盟に対して『喜々として中国に折り合おうとしている』と半ば公に批判したが、それは英国の動きが、米国のリーダーシップの低下へのヘッジと見られることを警戒し、クギを刺したものである」と指摘。さらに「日本の場合は、日本の加盟が米国を完全に孤立させることになるため、米国のリーダーシップ低下をさらに露わにさせ、中国に間違ったメッセージを送る恐れが強い。それを日米とも懸念している」と分析する。
また、船橋氏は、英国が「米国に父親のようにカツを入れよう」としているのに対し、「日本は母親のように米国を抱擁しているような、あるいは母親から離れまいとしてすがる子供のような姿」だと述べる。「……米国が十分にリーダーシップを発揮できず、影響力の空白が生じた時、米国の同盟国や友好国がそれを埋め、その体制を守る。これは新たな挑戦なのだ」として、日本はアジアに対して関心と影響力を持って向き合うべきだと主張している。
■ アジアにおける日本のODAの在り方
それでは、日本はアジアの中でどのように生きて行けばいいのか。『外交』第31号は、特集「新しい開発協力と日本の外交戦略」を組み、AIIBとも絡めて議論される経済協力のあり方について検証している。上智大学教授の宮城大蔵氏は、「和解と成長のアジアへ」のなかで、他の大国の援助が外交的な意思を通すための政策手段であったのに対し、日本の政府開発援助(ODA)は、国際社会復帰、賠償などといった戦後処理と深く結びついており、冷戦下では軍事力に代わり西側の体制支援を行う道具になってきた歴史を説明。また、日本の貿易黒字に対する米国の不満をかわす切り札としての役割も時代とともに終わり、90年代後半以降は、「……長らくつづいた『援助する側、される側』というアジアとの関係が、各種枠組み作りのパートナーへと変化した」と解説している。21世紀においては、中国への備えを固めるための援助ばかりでなく、「……未来に向けたアジア共通の課題を探り当て、そこに援助を用いる地道さと奥深さにも、いま一度注意が払われるべきであろう」と結んでいる。
■ 日本が目指すべき国際貢献
そのアジアでの開発援助の現状について、政策研究大学院大学教授の大野泉氏が、同じ『外交』の中の「『共創』と『競争』の時代への新戦略」で論じている。大野氏は、これまでの日本のアジア圏への経済進出は、円高対策による安い労働コストを求めた大企業の生産拠点移転が軸であったが、リーマンショック以降は、販路拡大を目指す中小企業が主軸になっていると解説している。その上で、これまでのODAによる経済援助は、製造業などの大企業の進出がもたらした日本式のビジネスモデルの中で機能してきたものであり、中小企業の進出が中心となった現在では、経営戦略やマーケティングといった中小企業の弱みをカバーするような官民連携が必要だと指摘している。
大野氏は、新時代に日本が目指すべき国際貢献として、四つの原則を挙げる。「第一に、知的・質的リーダーとしての地位を確保すること。……第二に、日本らしい優位性として、人づくり重視、現場力、高い技術力と品質・生産性への信頼、長期的コミットメントなどを打ち出すこと。……第三に、課題解決先進国として、産官学・NPOに蓄積された数多くの経験とノウハウをもって貢献すること。……第四に、上記を実践する方法として、今まで国内・アジアで構築した人材・組織ネットワークを総動員して、連携型協力で、世界の途上地域に対する知的開発支援を行うこと」だ。こうした原則に基づくアジアとのパートナーシップこそ、「……単なる量的な貢献でなく、知恵を駆使して日本の影響力を高めるグローバル戦略」の支柱になると訴える。
アジアの中での日本の在り方を考えるとき、どこの大国と組むかが大事なのではない。アジアに対して何ができるか、それこそがアジアにおける日本の価値を決めるのである。
2. ドイツから見た日本の歴史問題
◆「ドイツ対日歴史認識報道の国内的背景」 三好範英氏 [外交]
国内外の注目を集める安倍首相の戦後70年歴史談話。歴史問題での最大の相手国である中国・韓国との関係改善もあって、国内のメディアでは、安倍政権の歴史認識問題がそれほど先鋭化しなくなったようにも思える。しかし、一部の海外メディアでは、日本および安倍政権への厳しい見方が依然として根強い。この問題を、海外メディア側の問題としてとらえたのが、『外交』第31号が掲載した読売新聞編集委員、三好範英氏の「ドイツ対日歴史認識報道の国内的背景」である。
三好氏は、第2次安倍政権発足(2012年12月)の前後でドイツの日本に対する評価が悪化した例として、英BBCの世論調査を紹介。2012年と2013年の調査で、ドイツの日本に対する肯定的評価が、58%から28%に30ポイント急落し、否定的評価が29%から46%に上がった。この数字は、アジアでは、中国、韓国に迫る3番目の低さだという。三好氏は、この原因をドイツメディアの報道に求めている。「安倍政権が掲げるアベノミクスや原発再稼働方針は、均衡財政施策や脱原発方針と正反対であり、これらの点でも独メディアの日本報道は極めて否定的だが、安倍政権の核心にあるのが国家主義と修正主義という認識である。こうした報道が、ドイツの対日イメージ悪化に影響していると見ても、あながち的外れとは言えないだろう」との主張だ。
また、「……筆者が英米メディアと比較した限り、こうした傾向は特に独メディアに顕著と感じる。確かに歴史認識問題について、先進国メディアは概して安倍政権に厳しい立場をとるが、英メディアは過度な倫理的糾弾に走らない中庸を感じるし、米メディアには個々の論調には厳しいものがあるが、メディア界全体を見れば多様性がある」とも指摘する。
こうした分析をふまえて、三好氏は、ドイツ人の日本に対する厳しい視線の背景として「ナチズムの過去を糾弾され続けたドイツの知識人は、いわば贖罪を誇る、という屈折した形で心理的バランスを図ってきた面がある」と分析。戦後の贖罪や補償の努力は評価に値するとしつつも、「本来は個人の倫理であるはずの贖罪意識がイデオロギー化し、自由闊達な言論のやりとりを封じてしまう。……そして、倫理的ゆえに他者への攻撃は過度に激しくなりがちである。……こうしたドイツ人の心理的傾向は、学者、政治家、外交官など広範な知識層に共有されており、ジャーナリズムも例外ではない、ということなのだろう」と述べている。
三好氏は、両国の関係について、「歴史認識問題に過度に焦点を当て、現政権を倫理的に糾弾してやまない独メディアの報道姿勢は、日独関係にとって不幸である。……日本メディアもまた歴史認識問題に絡み、ドイツのある側面を都合よく取り出し、利用するかのような姿勢はもはや慎むべきであろう。そして、両国関係の多様な可能性にもっと目を向けるべきだろう」と締めくくっている。
※このページは、公益財団法人フォーリン・プレスセンターが独自に作成しており、政府やその他の団体の見解を示すものではありません。