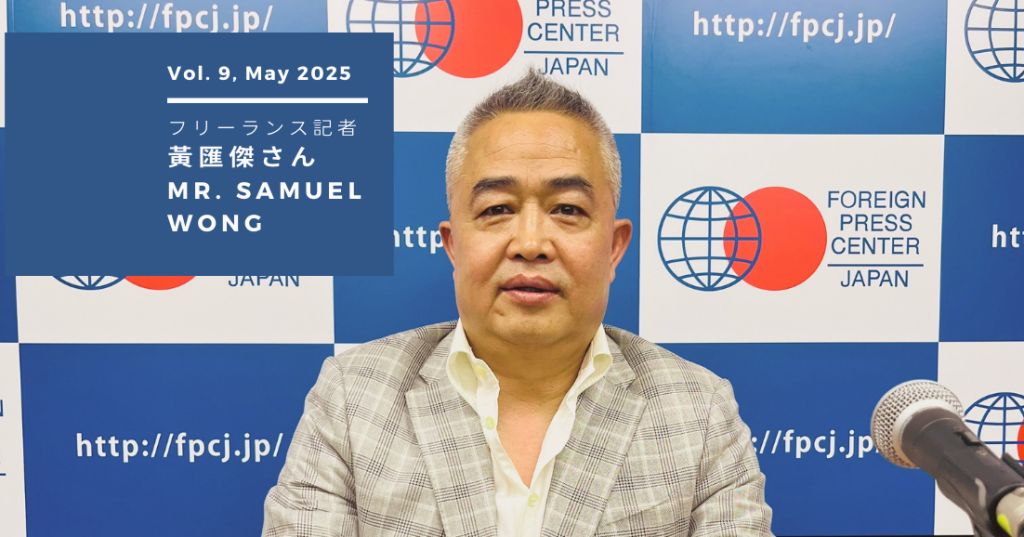【外国記者の素顔に迫る】「The Foreign Press」Vol. 9 黃匯傑さん(フリーランス記者)Mr. Samuel Wong
フォーリン・プレスセンター(FPCJ)の「The Foreign Press」の第9号をお届けします。現在、日本では、世界約30の国・地域、145の報道機関に所属する記者約430人が、日本各地を取材し世界に伝えています(FPCJ調べ)。こうした「記者」には、記事を書く記者/テレビ・ラジオのレポーターのほかカメラなどの技術スタッフ、さらに取材先のリサーチから取材調整、取材当日の現場対応を行うコーディネーター兼通訳など様々な役割の人々が含まれます。また、外国記者といっても、日本で採用された日本人スタッフも多く、その割合は全体のおおよそ3人に1人となっています。この企画では、このように多様性あふれる記者をご紹介します。皆さまにおかれましては、今後機会がございましたら、可能な限り彼らの取材にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
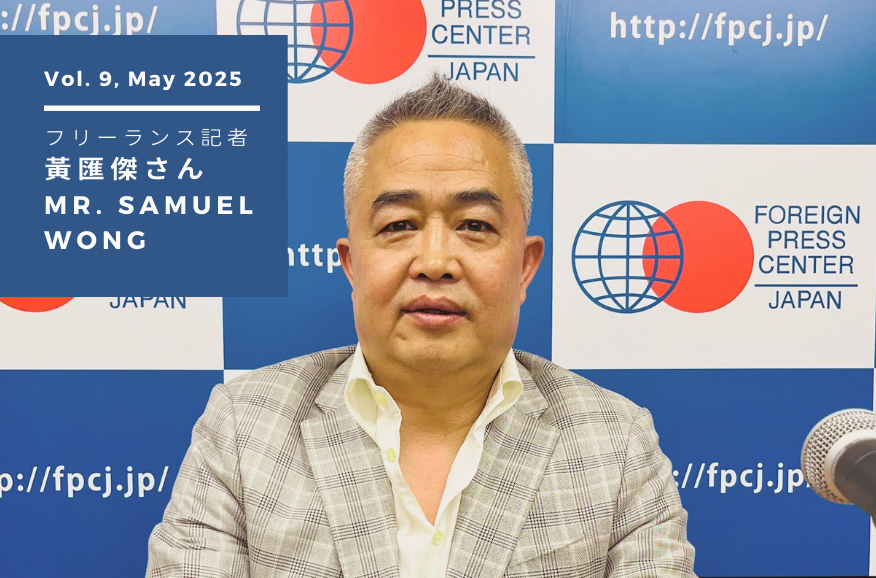
【日本と香港の架け橋に】
「12月23日の天皇陛下の誕生日にあわせて、「文匯報」(注1)のホームページに特設の祝賀ページを立ち上げたら、在香港の日本国総領事館、日本企業、日本メディア関係者はもちろん、香港メディアも皆一様に驚いていました」。新米ジャーナリストの頃の思い出を尋ねると、黄さんは興奮気味にこう答えました。
どうしてそんな破天荒なことをしたのかとさらに聞くと、今世紀初めの香港において日本の存在感は圧倒的だった、日本と香港の経済交流は隆盛を極め、数えきれない数の日本企業が進出し、数多の日本料理店が軒を連ねて活況を呈していたと黄さんは語ります。そのような時代背景の中で、日本や日本文化を読者に分かりやすく説明し、日本と香港の交流をより一層盛り上げたいと熟慮したうえでの決断だったと明かします。
【記者としての日本との関わり】
ジャーナリストになったのは「運命」だったと黄さんは語ります。黄さんは学生時代に日本のドラマや映画、歌謡などに魅了され、日本語を学ぶために1990年代中盤に1年間日本に留学しました。帰国後に就職活動を始めたものの、折しも香港は金融危機の只中にあり就職先は見つからず。途方に暮れたものの、友人の多くが記者を目指していたこともあり、新聞社をお試し受験したところ、日本語の能力を見込まれ「文匯報」に採用されました。
入社後は、香港に進出している日本企業への取材や各社を紹介するホームページの作成に精力的に取り組みます。上述の天皇陛下の生誕祝賀ページの作成もこのころの武勇伝です。その後「大公報」(注2)に活躍の舞台を移した黄さんは、経済交流に一層邁進し、日本貿易振興機構(JETRO)事務所と連携して日本企業100社を案内して中国広東省を訪問し、日中の経済交流の橋渡し役を務めたこともあったとのこと。黄さんは、こうして日本企業や日本メディア関係者との濃密なネットワークを構築し、その関心も日本企業の紹介や経済交流の実現から、日本と香港・中国の友好親善、相互理解の促進へと進化していきます。
【駐日特派員として】
2012年末に第二次安倍政権が誕生すると、日本の政治経済情勢を一層丁寧にフォローする必要性を感じた「大公報」は、黄さんに白羽の矢を立て、初代の特派員として東京に派遣しました。活躍の場を得た黄さんは、まるで水を得た魚のように、今度は東京から香港・中国への進出を計画する日本企業を取材し、現地企業とのマッチングに東奔西走する忙しい日々を過ごします。そして3年が過ぎ帰国が近づく中で、黄さんは独立を決意し、フリーランス記者として日本に残り、日本と香港・中国の経済交流や友好親善の促進への取組を続けていくことになりました。
その後は、フリーランス記者として、香港や中国のメディアの依頼を受けて取材し出稿する多忙な日々の中で、Weibo(微博/ウェイボー)に自身のメディアを立ち上げて日本文化を中心に発信を続けています。
【西洋文明と日本の伝統文化の融合への驚き】
 黄さんの日本への関心は、上述のとおりそのソフトパワーへの純粋な興味からスタートしましたが、日本留学から「文匯報」や「大公報」での数多くの日本企業との関わりを経る中で質的に変化していきます。1997年以降、香港の対外関係は「香港からの対外的な関係」から「中国・香港からの対外的な関係」へと質的に大きく変容を遂げました。その激動の中で、黄さんは、日本と中国南部、香港・マカオとの関係の変化の動きを、主に経済関係を軸としながら、精力的に現場を周り人々と対話する中で吸収していきます。
黄さんの日本への関心は、上述のとおりそのソフトパワーへの純粋な興味からスタートしましたが、日本留学から「文匯報」や「大公報」での数多くの日本企業との関わりを経る中で質的に変化していきます。1997年以降、香港の対外関係は「香港からの対外的な関係」から「中国・香港からの対外的な関係」へと質的に大きく変容を遂げました。その激動の中で、黄さんは、日本と中国南部、香港・マカオとの関係の変化の動きを、主に経済関係を軸としながら、精力的に現場を周り人々と対話する中で吸収していきます。
黄さん曰く、日本での取材は驚きの連続で、社会構造から政治、経済の発展に至るまで強い文化的な衝撃を受けたとのことです。黄さんが思春期を過ごした香港は万事が英国モデルで管理・運営されており、学校でも英国流の厳格な社会モデルを学んでいたので、東洋人として時に文化的な違和感を感じたり、適応に苦労することがあったとのことです。しかし、訪日してみて、初めて「西欧文明と(日本の)民族文化と伝統が融合した、真正の非植民地的な生活様式を実感」したとのことです。
【印象に残る取材、取材の苦労】
 日本での取材の中でも特に印象深かったのは、2011年の東日本大震災以降のいくつかの災害取材だったとのこと。日本の整然として秩序ある災害対応にはいつも驚かされたとのことです。
日本での取材の中でも特に印象深かったのは、2011年の東日本大震災以降のいくつかの災害取材だったとのこと。日本の整然として秩序ある災害対応にはいつも驚かされたとのことです。
取材での苦労について尋ねると、取材申請の煩雑さや取材先とのコミュニケーションの困難さをあげました。例えば、黄さんがある企業を取材する場合には、まず自分がどんなメディアに所属しているのかを丁寧に説明し、取材先からの信頼を得てからでなければ取材をスタートできないことが多いとのことです。また、日本では事前に提出した質問の内容次第では最終的に取材を断られるケースもあるとのことでした。
【今後の関心事項】
 2025年は北東アジアにとって重要な年になると力説する黄さん。台湾海峡の危機や世界的な経済金融危機、中国のバブル崩壊の可能性、さらにはトランプ政権の方向性が見通せないなど課題が山積する中で、世界の未来がどうなるのか、この一年の変化を見守る必要があると言います。
2025年は北東アジアにとって重要な年になると力説する黄さん。台湾海峡の危機や世界的な経済金融危機、中国のバブル崩壊の可能性、さらにはトランプ政権の方向性が見通せないなど課題が山積する中で、世界の未来がどうなるのか、この一年の変化を見守る必要があると言います。
黄さんから見ると、日本は平和な楽園であり、外資や外国人観光客を吸収する努力をしてサービス業を発展させているが、米国と同様に産業の空洞化や製造業の海外移転が一層深刻化するのかどうかの瀬戸際にあり、慎重な観察が必要と語ります。また、日本が米中関係の狭間でどのような外交を展開するのかや、日本は朝鮮半島からの脅威にも直面しているため、日米同盟の推移や平和憲法が改正されるかなどの変化も注視しているとのことでした。
香港に拠点を置く繁体字中国語の日刊新聞。中国共産党の政策に沿った論調が非常に鮮明で、香港の左派紙と称される新聞の一つ。中国政府から中国大陸での発行・販売が認められている。
中国、香港の新聞。20世紀初頭に天津で創刊され、今も香港で中国共産党の機関紙として発刊が続いている。中国語新聞としては発行期間が最も長い。